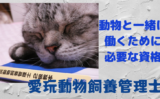1964年のイギリス。
「ルース・ハリソン」が【アニマル・マシーン】という本を書き、
近代畜産への鋭い批判と警鐘を促すと
イギリス国内では激しい議論が巻き起こったんだ。
ルースハリソンと【アニマル・マシーン】
それはね、動物の『本性』を無視した飼育を行い、
「動物農場」が「動物工場」となってしまった社会的背景のなかで、
農場動物の悲惨な実情を書いたものらしい。

ウシさんや、ブタさん。
ニワトリさんがどんな目に遭っていたか、想像したことある?

きっと、こんなほほえましい光景を思い浮かべると想うけれど
でもそれはアニメや、カレンダーやポスターなどの写真の中で描かれた【イメージ】でしかなくて、本当は、
本当はね・・・・。
1955年から始まった「近代畜産農業」の実態
イギリスとアメリカから始まったって言われている、第二次世界大戦が終わった1955年の頃から近代畜産農業が「農場」っていうやつは

「農場」なんかじゃなくて、「工場」だったんだ。
太陽の陽も当たらず、
わずかな空間にウシやブタ、ニワトリを詰め込めるだけ詰め込んじゃうから
彼らは手足を伸ばすこともできない状態で、それでもなんとか生きている・・・
生きているというより、ただ「呼吸しているだけ」

食肉専用に育てられるブロイラー用の若いニワトリは、
ヒヨコのときに何千羽という数で窓もない鶏舎にぎゅぅぎゅぅ、ぎっしりと詰め込まれたんだ。
窓がないから、夏は炎熱地獄。
ほこりっぽいし、じめじめ、むしむしとしていて、すごく臭くなるんだ。
そんな環境だから病気になっちゃうし、
しばしば大量のニワトリが死んじゃうから、抗生物質やら薬剤がエサの中に混ぜられる。

ウシは、生まれてすぐに母ウシから引き離されると真っ暗な畜舎に放り込まれ、
すぐに身動きができないように首を鎖でしばりつけられちゃうから、
真っ暗な畜舎で身動きも取れず、
横になって寝ることもできず、
あげくは床には自分たちの糞尿だらけ。
しかも、それは片づけられることがない。
と殺されるために外に連れ出される、この一日だけ、
彼らはようやく、お日様の光を浴びることができたんだ。

しかも、ほんの数時間だけ。
まぶしい太陽の下に出た数時間後には、その命はもうこの地球上にはない。
乳牛だって生産性がなくなれば、殺されちゃう。

動物たちはつねに人間によって「優良」と「劣悪」に仕分けされ、
「劣悪」とされたらすぐに殺されてしまう。
安いコストで人間の手間や面倒をかけず、より多くの卵、乳、お肉を提供できるのが「優良」
そうでないものは「劣悪」
たとえば昨日まで「優良」とされていた乳牛が、
今日、要求されているだけの量のお乳が出せなくなった時、
すぐに「劣悪」のラベルを貼られ、と殺場行きになっちゃうんだ。
スーパーで並ぶお肉。
一体、どれだけのウシさんが殺されたんだろうね。

それがちゃんと
人間のため、
人間のお腹の中に入っていればいいけれど・・・ね。
今、ようやく問題になっているけれど
時間が経ったお肉は売り物にならなくなっちゃって、
たいはんは食べられることなく、そのまま廃棄処分されちゃうんだ。

アニマルマシーンという書籍
1964年。
イギリスで「ルース・ハリソン」さんが【アニマル・マシーン】という本を書いたの。
彼女はロンドンで、
病気や孤独のために社会から落伍した人々を社会生活に復帰させるボランティア活動に専念していた主婦さん。
農場動物の悲惨な実情を描いた【アニマル・マシーン】の中で
工業的畜産って、何?
集約的飼育って、わかる?
そんな問いかけを序章とした、
イギリスにおける「ブロイラー用のニワトリ」の問題から近代畜産を告発した最初の書籍らしい。
ハリソンさんは
食物とは、人間を健康に生かし、
さらにその健康を子孫の代まで引き継いでいくために不可欠なもの。
そのために、健全な土・健全な植物や動物をわれわれの責任において作り
維持していくことが必要。しかし、事実は逆の方向に進もうとしている・・・
参考:愛玩動物飼養管理士2級受講テキスト「アニマルライツ」
と言っているけれど、
でも実は、動物に「何らかの権利がある」とは言ってはいないんだって。
それはね
人間の権利もないがしろにされている状況で、動物の権利を主張することに賛同しがたい。
というものなんだとか。
ただし、
人びとの良識と責任において、正しく動物を取り扱うこと。
動物の持つ「習慣」、「生活様式を尊重」することが、最低限必要であろう。
と。

ハリソンさん自身はね
乳製品と卵だけは食べる【乳卵菜食主義者】だったんだって
日本でもこの「アニマル・マシーン」の書籍が、1979年に日本語に訳されて出版されたんだけれど
もう長い間「絶版」していて、この本の存在を知る人は、ほとんどいないんだ。

ぉかーちゃんも、
こぅやって調べていくまで知らなかったもんね
一度、読んでみたいかも。
(もしかしたら、読んでいるうちに具合が悪くなるかもだけど)
「アニマル・マシーン」には、こんなことが書いてあるんだって。
『アニマルマシーン』近代畜産にみる悲劇の主役たち
本書のなかで論じているのは、家畜動物の取り扱いをどうするかの問題だけではない。
むしろ本当に関心をもって論じたのは、
私たち自身の生活の質が落ちてきており、これにどう対処すべきか。という点であった。農場の動物を、生まれてから屠殺するまで永久に閉じ込めて収容するシステムが、
この三十年ばかりの間に着実に定着し、その地盤を築いてきた。(中略)
これらのシステムのなかでも極端な方になれば、数限りない動物をぎっしりと詰め込むので、
彼らは手足を伸ばすこともままならず、「やっと生きている」といった始末である。彼らは目のあらい格子床の上に立っているのだが、
その下ではいつも自分たちの糞尿が鎮座していて、どいてくれない。そして「おひさま」を拝むことができるのは、
屠殺のため外に連れ出される時の一回だけ・・・ということもしばしばである。(中略)
農業はやはり、生命のない物体を扱っているのではなくて、
「生きとし生けるもの」を扱っているのである。「食糧の供給」という点で私たちは、現在も農業に依存しているし、
将来も依存するのだから、
未来の子孫から「農業」を奪うようなことはできない。だから
連綿と続く生命の継承を考慮に入れないような処置をとってはならない。私たちの生命が食物の絶えざる供給に依存していることは当然であるが、
参考:1979年 ルース・ハリソン近代畜産にみる悲劇の主役たち
もっと正確にいえば、
健康によい食物の、絶えざる供給に依存しているのである。
読んでみたい・・・かも。
家畜飼育の基本となる「5つの自由」
【アニマル・マシーン】が出版されて、わずか6週間後。
産業動物の福祉増進を目的とする実態調査を行う「ブランベル委員会」が、イギリス政府の委嘱によって設立されたんだって。
委員会の報告は翌年には公開され、その中で今日の家畜飼育の基本となる次の理念が勧告されたんだ。
どんな条件の下であろうと、
家畜には少なくとも動作における5つの自由が保障されるべきである。
その自由とは、楽に向きを変えることができ、自分で毛並みをそろえることができ、
起き上がり、横たわり、四肢を伸ばすことができる自由である
というもの。
現在では新しい5つの自由として唱えられているんだ。
どんな条件の下であろうと
家畜には少なくとも「動作」における5つの自由が保障されるべきである。
楽に体の向きを変えることができ、
自分で毛並みを整えることができ
起き上がり、横たわり、四肢を伸ばすことができる
というものなんだ。
○ 飢え・渇きからの自由
○ 不快からの自由
○ 苦痛からの自由
○ 恐怖・抑圧からの自由
○ 自由な行動をとる自由

【新しい5つの自由】、とてもとても重要でーす!
ここ、テストでまーす!
しっかり覚えてくださーい!
ルース・ハリソンも
「食糧の供給という点で私たちは現在も農業に依存しているし、将来も依存するのだから、未来の子孫から農業を奪うようなことはできない」
そう言っているように【畜産業】を完全否定しているわけではないんだ。
現在の畜産業はかつてほどヒドくないはずだけど(そう信じたい)
それでも今もなお利益のために
殺さなくてもいい命まで殺し、結局は消費しきれず、余ったものはいとも簡単に廃棄する。
あるいは、「病気になったから」と、簡単に殺処分する。
・・・他の動物に伝染しないように。
それは「仕方がない事」なのかもしれない。
けれど、今一度
動物の立場になって思いやりをもつことが求められているのだと思う。

人間が、「クマに襲われたー!」とか。
他の動物に殺されちゃったりすると、ニュースで「あーだこーだ」と騒わぎ、
「農作物が荒らされたー!」って言うとシカやイノシシ「害獣」扱いして殺したり。
あーや、こーやと騒ぐ前に
人間が一番、他の動物を殺しているんだ。っていうこと、気づいてほしいんだ。
他の生き物の「命」をこんなにも犠牲にして生きている イキモノ って人間くらい、だよね。
だからせめて・・・
せめて・・・
食べられちゃう動物への【5つの自由】だけは大事にしてほしい。
・・・そう願うんだ。
参考文献:愛玩動物飼養管理士テキスト2級-1