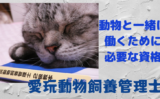人間社会に貢献する動物たち
動物介護活動(アニマル・アシステッド・アクティビティー)
これは、動物が人間の心に多大な影響を与えることができる。ということで今、
人間の社会で実施されているもの。
最近では動物介在教育(アニマル・アシステッド・エデュケーション)も新しく注目されていて、
国際的にはこれらを総称したのが
Animal Assisted Interraction (動物介在)
もしくは、
Animal Assisted Intervention(動物介入)
なんだ。

ちなみに
よくアニマル・セラピー(Animal Therapy)っていう言葉を聞くけれど
これは少し、正確な表現じゃないんだって。
人間の医療や福祉の現場に参加する動物たち
Animal Assisted Interraction (動物介在)
もしくは、
Animal Assisted Intervention(動物介入)
「これらはいったい何のことじゃ?」って言うと

人間の医療や福祉の現場に、
ボクたち動物も参加させてもらえる!
という事なんだけど、
そこにはふたつの形態があって
ひとつめは「動物介在療法」
治療過程の「医療」「福祉」の専門家が明確な治療目的を持って
ボクたち動物と一緒に、患者(対象者)の治療や改善経過を記録しながら行うもの
ふたつめは「動物介在活動」
子供や高齢者、病気や障害を持つ人を対象にして、彼らの生活の質を向上させることを目的で
ボクたち動物に触れ合ったり、一緒に遊んだりするいわゆる「レクリエーション的な活動」のこと。

動物ふれあい活動なども
この「動物介在活動」に含まれるんだ

動物介在療法のような、改善目的とか記録は必要としないけれど、
でもボクたちと触れ合った結果として
寝たきりだった高齢者の人が、車いすに乗って生活できるようになったり
表情が豊かになったり、会話が増えたり。
ボクたちが大活躍した報告も多いんだよ。

と言っても。
ボクたち「猫」じゃなくて
犬の活躍がほとんどなんだけど、ね

人間社会で活躍するための約束ごと
とはいえ。
療法にしても、
活動にしても
これにはいくつかの共通した約束ごとがあるんだ。
それはまず「癒し」の正体になるヒトと動物の本来の関係に基づいた実施基準を決めておくこと。
って、ちょっと難しい言い方をしているけれど、つまり
ヒトと接する現場で、
ボクたち動物が本当に良い影響を与え、本来のチカラを発揮するためには、
どんな場面でも楽しい気分になれる性格(性質)の子じゃなきゃダメなんだ。

ボクたちを見守ってくれる人間たちの言うことを、ちゃんと聞ける
社交性のある子じゃないと、ね。
それが最低条件。
たとえどんなに「オスワリ」や「フセ」が上手に出来たとしても、
落ち着きがなかったり、人見知りしちゃう子たちは、このお仕事には向いてない。
だって、
ひょぃ。と無造作に差しのべられた手に驚いて、怖がって
噛みついちゃったり、ひっかいちゃったりしたら大変だもんね。
だからこれは絶対のお約束ごとなんだ。

性格が良くても、参加できない子がいるんだ
たとえどんなに社交性のある子だったとしても・・・
医療や福祉の現場のお手伝いをする動物は感染症などのリスクがないように
健康診断や予防接種、
皮膚や被毛のお手入れがしっかりされている子じゃなきゃダメ!
だからどんなに珍しくても
どんなに可愛くても
どんなにおとなしくても・・・

「野生種(動物)」って呼ばれている子たちは
この療法や活動には参加できないんだ・・
たとえ見た目はどんなに可愛くて、どんなに大人しい子でも
ヒトと動物との「共通感染症」の危険がいっぱいだし
どんなにヒトの手に慣れているからと言ってもふとしたきっかけで、びっくりして驚き、
興奮してパニックになってしまうとヒトの手で抑えるのは困難になっちゃうから、ね。

パニックになった動物の力って、それはもうほんとうに、
びっくりするくらい強いものなんだ
こんな可愛い子でも何かの拍子に驚いてしまって、ちょっとでもパニックになったら、
人間ひとりの力では抑え込めないくらいの力があるんだよ。

人と動物が助け合って生きていくために
ボクたち動物は結構、「ストレス」を感じやすいんだ。
だから、飼い主以外の他の人間と「ふれあう」活動は
人間の都合や要求を優先するのではなくボクたちの性格にあった条件の中で行わなければ

ヒトと動物、
どちらもツラくなっちゃう結果に・・・
こうした活動をする前に人間たちは、
いろんなお勉強や教育を受けて、事前の準備をいっぱいしてくれるし、
ボクたちも
人間のお手伝いをするときはその前にいろんな検査や訓練を受けたり。
動物も人間も、みんなが楽しく過ごせるために、頑張ってるんだ。

人間と、ボクたち動物が助け合っていける世界って、
本当に素敵だよね。
と、言っても。

ボクたちは、おかーちゃん、ばぁば、じぃじ以外の人間が怖し、
触られるのが大嫌いだから人間の社会での活躍は無理だけど、ね。
でも、おかーちゃん、ばぁば、じぃじのことはしっかり「癒し」てるよ。
犬ってすごいよね

犬の中には、
人間の生活を支える重要な任務を任されている仲間たちもいるんだ
身体に障害を持つ人々の生活を補助する犬たち
世界のあちこちに、
いろんな障害を持つ人たちの生活を補助する犬たちがいるんだけれど
日本の法律で認められているのは
視覚に障害がある人の生活を補助する【盲導犬】
聴覚に障害がある人の生活を補助する【聴導犬】
身体が不自由な人の生活を全面的に補助する【介助犬】
なんだ。
盲導犬
視覚に障害をもつ人のために歩行誘導をするように訓練された犬たちのこと。
曲がり角や段差で立ち止まったり、さまざまな障害物をよけたりしながら
視覚に障害がある人が安全に歩くことができるように訓練されているの。
簡単そうに見えて
とても難しいお仕事なんだ。
法的に認められている補助犬の中では、
もっとも古くから日本で活躍しているんだって。
聴導犬
聴覚に障害がある人に「音」を知らせるために訓練された犬のこと。
ドアの呼び鈴や、電話の呼び出しの音、
ブザーの音や、飼い主さんを呼ぶ声、
ヤカンのお湯が沸く音とか、危険を知らせる音
いろいろな音を聞き分けて適切な方法で伝えたり
音のするほうまで誘導したりする訓練を受けているの。
介助犬
体の不自由な人を手助けする犬のこと。
日常生活のいろんな場面の中で
体の自由に動かすことのできない人の手や足となって動けるように訓練されているの。
盲導犬や聴導犬と違って、介助犬になるためには
介助犬の補助を必要とする人の障害の種類や重さがさまざまだから
必要とする人のニーズに合わせて、
落としたものを拾ったり
ドアを開けたり
エレベーターのボタンを押したり・・・
より細かく訓練しなきゃならないんだ。

そんなことができちゃう「犬」ってスゴイよね!
補助犬たちの存在は、
単に障害を持つ人たちの生活の不自由さを取り除くだけじゃなく
その人たちが自立したり、社会参加できるように大きく貢献しているんだ。
障害のある人が、補助犬を連れて外出することにより、
外出先で大変な思いをしたり
危険な目に遭ったり・・・
そんな障壁が減り、外出の頻度が増えたという声が聞かれるけれど
それは、補助犬を必要とする人たちだけがその恩恵を受けているわけではなく
障害がある人も積極的に社会に参加することで、社会全体が豊かになる。
それこそが、補助犬として活躍する「犬」たちの重要な役割なんだ。
補助犬と暮す責任
障害を持ち、補助犬の助けを必要とする人は
生活を補助し助けてもらうと同時に、その子たちの「保護者」にならなければなりません。
補助犬はたんに障害を補助する「介助器具」ではないのです。
生活のパートナーであり、
命をもつものとして接しなくてはならないのです。
そのためには、自分と生活を共にする「補助犬」の管理をしっかり行い
福祉を守り、
信頼される飼い主になる必要があるのです。
補助犬になる犬たちは専門的な訓練を受ける前に
補助を必要とする人と無理なく社会参加(生活)ができる性格であるか?
相性が適正であるのかどうかを十分に審査されるのです。
参考文献:愛玩動物飼養管理士テキスト2級-1
資格者は全国に約20万人のペットの資格!【愛玩動物飼養管理士 2級・1級】