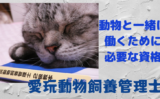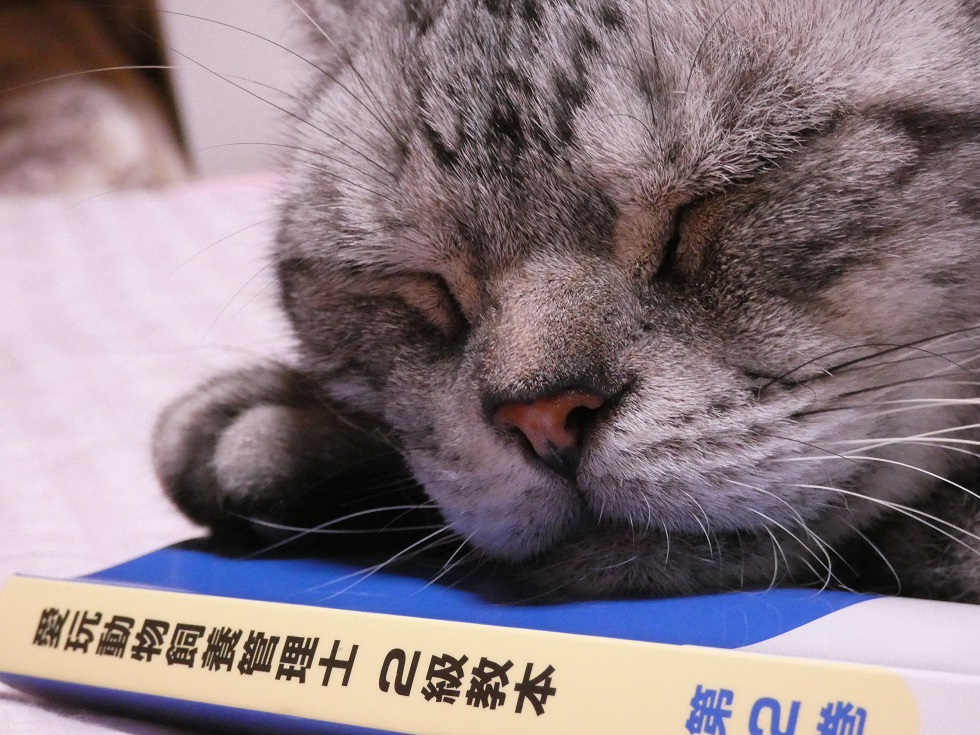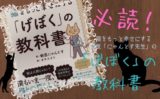ペットフードを購入する時、数多くあるフードの中から

ぅ~ん。
どのフードが安全だろう?
危ないモノ、使ってないかしら・・・?
ってつい、悩みますよね。
大事な家族の胃の中に入れるもの。
「できるだけ安全なものを食べさせたい」と思うのは誰もが思うこと。
でも、ネットで調べると、いろんな情報であふれていて、調べれば調べるほど、どんどん解らなくなってきてしまいます。
でも実は・・・

結論から言うと基本、
国内で売られているのは、ある程度
どれも「安全」と言っても、大丈夫なんですよ。
なぜなら国内で販売されているフードは、
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」いわゆる「ペットフード安全法」というもので
国の管理のもと、厳しく守られているからです。
日本における「愛玩動物の飼養」は年々増加の傾向に。
それに伴い愛玩動物用飼料も、「ペットフード」として企業によって生産・販売されたものを購入し、食べさせている飼い主さんも多くいるため、フードに対する安全性が高まっています。
人と「愛玩動物」のかかわり方の変化に伴い、
これまで規制されることのなかった「愛玩動物用飼料(ペットフード)」についても、2009年になってようやく食物の安全性確保に関する法令も定められました。
違反した業者や違反者には、厳しい罰則もあります。
では「ペットフード安全性」とはどんな法律なのか?
概要を一緒に見ていきましょう。
最後に、「危険」と言われている「酸化防止剤」「ミート」についても書いてます。

「ペットフード安全法」については
愛玩動物飼養管理士の教本の中でも書かれています

法律制定の背景と経緯
2007年(平成19年)3月
米国によって製造・販売されたフードの中に、化学物質の「メラミン」が混入されていたことが原因で、アメリカを中心に犬や猫などのペットたちが、尿管結石による腎障害で死亡する事件が発生。
それは数千頭規模で相次ぎ、その後の調査で、
これらの原因がペットフードに混入されていたメラミンという物質であることが判明。
2007年(平成19年)6月
メラニン混入のおそれがあるペットフードが、日本にも輸入・販売されていることが判明。
販売業者による自主回収が行われる騒動に。
このため、これまで日本にペットフードの安全を確保する法律がなかったことから、
2007年(平成19年)8月
環境省と農林水産省が共同で、有識者からなる「ペットフードの安全確保に関する研究会」を設置。
2007年(平成19年)11月
研究会で幅広く論議された、ペットフードの安全を確保するため方策の報告をふまえ、
ペットフードの安全確保上の課題と対応のありかたを取りまとめ公表。
このとりまとめによって、動物愛護の観点から、
ペットフードの安全確保は緊急に取り組むべき課題とされた。
そのためには、事業者及び民間団体の自主的な取り組みが重要である、とする一方で
そこには強制力がなかったため、
◇ すべての事業者が自主的な取り組みをするということが担保できないこと。
◇ 予期せぬ事故などに対しても、すぐに実効性のある対策が打てない可能性があること。
ゆえに、法規制の導入が必要であると提言。
その提言を受けて、
2008年(平成20年)3月
環境省と農林水産省は「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(案)」を作成
第169回国会へ「新法」として提案。
全会派の賛成によって同年6月11日に可決・成立。
2009年(平成21年)6月1日から施行されています。
法律が求めるもの
第一章:法律の目的・対象となるもの
第一条:法律の目的
この法律の目的は
愛玩動物(犬・猫)用として作られるペットフードの製造などに関する規制を行うことで、ペットフードの安全性を確保し、愛玩動物(ペット)の健康を護り、動物の愛護に寄与することとされています。
(寄与:役に立つことを行う、貢献する)
第二条:定義
【ペットフード安全法の対象動物】
愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令(平成20年政令第366号)において、
愛玩動物とは「犬」及び「猫」に限られています。
◇理由
①ペットフードの出荷量に占める割合による
犬用が約60%
猫用が約34%
(平成18年度ペットフード工業会調査による)②「ペットフードの安全に関する国民意識調査」によるもの
(平成19年10月 環境省・農林水産省調査)
ペットフードの安全性を確保するために今まで以上に規制が必要なペットとして
犬:約89%
猫:約80%と、大半を占めていることから「犬」と「猫」に限定されている。
環境省・農林水産省【愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行の状況】
したがって、
それ以外の小動物は、一般的に「愛玩動物」として育てられているものであっても
この「ペットフード安全法」の法律の中では対象動物にはならない。
【愛玩動物用飼料の範囲】
この法律で言う「愛玩動物用飼料」とは、
愛玩動物としての「犬」「猫」に栄養を与える目的として使用されるものをいいます。
フード(総合栄養食・一般食)以外でも
〇 ミネラルウォーター(愛玩動物用)
〇 生肉
〇 スナック(おやつ)
〇 ガム
〇 サプリメント
これらも「栄養を与える目的」として使用されることが明らかであれば
愛玩動物用飼料の扱いに含まれます。
ただし、
同じように犬や猫に与えられるものでも、動物用医薬品等とされているものは除かれています。
【対象業者】
製造業者
この法律で対象となる「製造業者」とは、ペットフードの製造する業者のことですが
その中には飼料を配合したり、加工する場合も含まれています。
輸入業者
この法律で対象となる「輸入業者」とは
ペットフードを輸入する業者のことを言います
販売業者
この法律で対象となる「販売業者」とは、ペットフードを販売する業者のことで
製造業者及び輸入業者以外の者を言います。
第三条:事業者の責務
ペットフードの製造業者・輸入業者・販売業者はそれぞれ事業を運営するにあたり、
自らが「ペットフード」の安全性の確保について「第一義的責任」を負っていることを認識し、
◇ ペットフードの安全性の確保に係る「知識」および「技術」の習得
◇ ペットフードに使われる原材料の安全性の確保
◇ ペットの健康が害されることを防止するため、必要に応じてペットフードの回収
そのほか必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
第四条:国の責務
この法律の施行に関し、国の責任として
ペットフードの安全性に関する情報を収集・整理・分析し、
それを関係者に提供するように努めなければならないとされています。
第二章:ペットフードの製造等に関する規制

第五条:基準及び規格の設定
農林水産省大臣及び環境大臣は、
ペットフードを使用したことによりペットの健康が害されることがないように防止する観点から
「農林水産省令」「環境省令」でペットフードの製造方法や表示についての基準を定めるとともに
ペットフードの成分について規格を定めることができるとされています。
この規定に基づいて、販売用のペットフードには「基準・規格」が定められています。
(ただし、そのペットフードを製造する事業場において使用されるものは除く)
なお、これらの基準や規格の制定、改正、廃止しようとするときは、
民意を反映させるという意味で、
農林水産省の「農業資材審議会」および環境省の「中央環境審議会」の意見を聴く必要があります。
第六条:製造などの禁止
規定により、基準・規格が定められた時は当然のこととして
この基準や規格に合わないフードの製造などは禁止されます。
禁止される事項は次の通り
第七条:有害な物質を含むペットフードの製造等の禁止
農林水産大臣及び環境大臣は、
ペットフードの使用が原因となって、ペットの健康が害されることを防止するために必要があると認める時は、民意として農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴き、製造業者・輸入業者または販売業者に対し
製造・輸入・販売を禁止することができます。
この規定によって製造・輸入・販売を禁止した場合は、その旨を官報に公示し、
一般にも広く知らせることが義務づけられています。
第八条:基準及び規格に合わないフードの廃棄
農林水産大臣及び環境大臣は
製造業者・輸入業者・販売業者が
これらのペットフードを販売、または販売するために保管していた場合、
製造業者・輸入業者・販売業者に対して当該のフードを廃棄または回収を図るなど、必要な措置をとるように命ずることが出来きます。
第九条:営業に関する届け出
この法律に基づき、基準または規格が定められたペットフードの製造または輸入しようとする場合は、
事業(運営)の開始前に農林水産大臣及び環境大臣に届ける必要があります。
【必要な届け出事項】
この届け出に関し、基準または規格が定められたことにより
〇 新たに「製造業者」「輸入業者」となった場合
〇 届出事項の変更があった場合
〇 事業を廃止する場合
〇 事業を譲渡する場合
〇 事業を相続・合併・分割した場合
確定した日からその旨を30日以内に届け出ることが定められています。
第十条:帳簿の備え付け
ペットフードの製造または輸入を行う場合、製造業者及び輸入業者は帳簿を備えつけておき
ペットフードを製造し、または輸入、または販売業者に譲り渡した時は、
「名称」「数量」「相手方の氏名または名称」など
そのほか農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを2年保存することが義務付けられています。
第三章:行政等による取り組み
第十一条:報告の徴収
この法律の施行に伴う国の責務として、
フードの安全性に関する「情報収集」「整理」「分析」および「提供」のほかに
農林水産大臣または環境大臣は
「製造業者」「輸入業者」「販売業者」またはフードの「運搬業者」「倉庫業者」から、業務に関して必要な報告を求めることができます。
この報告の徴収は農林水産大臣・環境大臣がそれぞれ単独で行うことが出来ます。
その場合は速やかに、もう一方のの大臣に通知することが義務付けられています。
第十二条:関係職員による「立入検査」
農林水産大臣または環境大臣はこの法律の施行に必要なものとして職員に、
「製造業者」「輸入業者」もしくは「販売業者」またはフードの「運搬業者」「倉庫業者」の
〇 事業場
〇 倉庫
〇 船舶
〇 車両
そのほかペットフードの製造、輸入、販売、輸送または保管の業務に関係がある場所に立ち入らせ
フード、原料、業務に関する「帳簿・書類」そのほか物件を検査させ、関係者に質問させ、
検査に必要な限度でフードや原料を収集させることができる。
(ただし、フードまたは原材料をを収集させるときは時価によってその対価を支払う)
また、この業務を行う職員は、身分証明書の携帯と関係者への提示が必要となっています。
職人による立入検査などをそれぞれの大臣が単独で行った場合、
その結果をもう一方の大臣に速やかに報告することになっています。
第十三条:センターによる立入検査
職員の立入検査について、農林水産大臣が必要があると認めた場合
職員に替えて「独立行政法人・農林水産消費安全技術センター」に行わせることができる、とされています。
ただしこのセンターによる立入検査を行う場合は、立入検査などの期日・場所・そのほか必要な事項を示し実施しなければなりません。
センターによって立入検査を行った場合、その結果を農林水産大臣に報告することが義務づけられて報告を受けた農林水産大臣はその内容を、環境大臣に通知することとされています。
第十四条:センターに対する命令
農林水産大臣は、センターによる立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めた時、センターに対し業務に関し必要な命令をすることができます。
第十五条:輸出用ペットフードに関する特例
清掃などの禁止に関する規定において
輸出用のペットフードについては、政令でこの法律の一部の適用を除外し、そのほか必要な特例を定めることができます。
第十六条:行政権限の委任
この法律に規定されている大臣の権限について
農林水産大臣の権限いついては農林水産省令の定めるところにより「地方農政局長」が
環境大臣の権限については環境省令の定めるところにより「地方環境事務所長」が委任することができるとされています。
したがって、
行政による実際の業務は各地方の「農政局長」「地方環境事務所長」によって行われることになります。
第十七条:経過措置
省略
第四章:罰則

法律に基づき規制措置を行った場合、
多くはその違反者に対し「罰則」が定められています。
ペットフードの安全性の確保に関する法律の場合の罰則には次のようなものがあります。
第十八条:一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金に処せられる場合
① 製造禁止の条項に違反した者
② 有害な物質を含むフードの製造等の禁止条項に違反した者
③ 廃棄命令に違反した者
第十九条:三十万円以下の罰金に処せられる場合
① 事業開始前に届け出をしなかった者、または虚偽の届け出をした者
② 必要な報告を行わなかった者、または虚偽の報告をした者
③ 立入検査や集取を拒み、妨げ、もしくは忌避しこれらの規定による質問に対し答弁しなかった者、または虚偽の答弁をした者
第二十条: 法人の違反行為に対する罰則
法人の代表者または法人、もしくは人の代理人、使用人、従業員がその法人または人の業務に関して違反をした場合
① 第十八条にかかる違反をした場合:法人には1億円以下の罰金・行為をした人には100万円以下の罰金があわせて科せられます
② 第十九条にかかる違反をした場合:法人と行為をした人にはそれぞれ30万円以下の罰金が科せられます
第二十一条・第二十二条:二十万以下の過料に処せられる場合
① 事業に関する届出事項の変更を届け出なかった者、継承に関する届出をしなかった者、または虚偽の届け出をしたもの
② センターが、農林水産大臣の命令に違反した場合、センターの役員
第二十三条:十万円以下の過料の処せられる場合
業務に関する帳簿を備えず、または帳簿に記載せず、もしくは虚偽の記録をし、または帳簿を保存しなかった者。
「危険なフード」はない。ただ、どのフードだって「あう」「あわない」があるだけ
ペットの愛護や保護という点では、欧米諸国から50年も100年も遅れ、ペット後進国とも言われている日本。
それは、日本ではまだまだペットを「モノ」として、
飼い主の「所有物」として見ているところがあるからかもしれません。
例えば、ペットがいなくなって警察に届ければ「遺失物」扱いですし
ペットを保護して届ければ「拾得物」扱いになります。
そんな動物愛護や保護という点でかなり遅れている日本で、「ペットフード安全法」が施行されたのも、ごく最近です。

でもさ、日本の法律って結構「ざる」だし・・・

と、あれこれ疑いだしたらキリがないけれど
このように、現在のペットフードに関して「ペットフード安全法」という厳しい法律があります。
聴き馴染みのないメーカーや輸入業者であったとしても、
業務を始める前には必ず国(農林水産大臣・環境大臣)に「営業の届け出」をすることが義務付けらているので、コッソリ製造(輸入)したものを、コッソリ販売することはできません。
よく耳にするメーカーさんであれば、なおのこと。
いま、国内で販売されているペットフードに関してはどれも「安全」と言えると思います。
仮にもし、危ないフードを作っていたとしたなら、
それが発覚した時にはメーカーとして致命的になりかねませんよね。
ですのでメーカーや輸入業者は、法や規格の遵守し
フードを安く仕上げるために、粗悪な材料を使ったり、危険な材料を使ったり・・・
そんなフードを作るメーカーはいないはずです。
(そう信じたいです。)
現実には、すべての製品に目を光らせることは難しいようだ。
農林水産省の担当者は悩ましげに打ち明けた。「国内で流通する製品はランダムで抜き打ち検査をしているが、成分を分析するには大量のサンプルが必要。個人がSNSやフリマサイトで小袋で販売している商品だと、検査が難しことがある」
5/11配信:AERAdot.
酸化防止剤の不安について
例えば、フードについて調べているとよく、
どこそこのフードには「酸化防止剤」にBHA(ブチルヒドロキシアニソール)が使われていて
これには発がん性物質があるから危険、買っちゃダメ!と書かれているものもあります。
でもこれは、
「どれくらいの量まで投与したら健康被害が起きるのか?」という試験結果を正確に伝えたものではありません。
試験は「無害といえる量の上限」を探し出すため、マウスやラットを使って大量に投与する極端なもので、この試験の結果から、その量を100分の1にまで減らした量を1日摂取許容量として、
そこからさらに減らした量をペットフードに使用する際の使用基準に決められているそうです。
なので、もし成分表に「酸化防止剤(BHA)」と記載があっても
使用基準内であれば、科学的に安全が確認されているといえます。
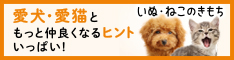
他の物質も、法第5条に基づき「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」によって含有量が厳しく定められています。
ちなみに。
添加物はないにこしたことはないのかもしれませんが・・・
「酸化防止剤」が使用される理由として、フードに含まれる脂肪は、光に当たったり空気に触れたりすると酸素と結びつき、酸化してしまいます。
脂肪が酸化することで、フードへの嗜好性が低下して食いつきが悪くなるばかりでなく、
嘔吐や下痢などの消化器の症状を起こすこともあります。
なので、
光や空気に触れてしまうと脂質の酸化の進みやすい「フードの質と安全性」を守るために、「酸化防止剤」は使われているのです。

フードの疑問について
東京猫医療センター院長の服部幸先生のお話は目からウロコな、
いま、話題?になっている「グレインフリー」についてなど
「なるほどー!」と思えるものばかり。
11:20くらいで「添加物(酸化防止剤)」のお話もされていますよ。
ミートミールの不安について
また「ミートミール」についても、いろいろ騒がれています。
「ミール」とは、肉類を乾燥させて粉状にしたもの。
加熱乾燥することで、生肉よりもタンパク質を凝縮させることができ、よりたんぱく質の多いフードを作ることができます。
ミートミールで問題視されているのは、いわゆる4Dミートと言われる
□ Dead 死骸となった動物
□ Diseased 病気の動物
□ Dying 瀕死の動物
□ Disabled 障害のある動物
これらの使用です。
AAFCO(米国飼料検査官協会)の定義の中にこの説明がないので、「4Dミート」が絶対に使われていない、というわけではないようです。
そのため、必要以上に「不安」を煽るフード会社もあるようです。
FEDIAF(欧州ペットフード工業連合会)では動物性原材料で使用できる基準が定められていて、
動物性タンパク源は、獣医師の監視下で屠殺された動物や管理された魚や魚介類で、EU法の基準を満たさないといけないとされています。
FEDIAFでは使用してはいけない基準も定められていて、
□ 屠殺時に人が消費するのに適さなかった肉
□ ロードキルや病気の動物など
と、あります。
ミールは決して悪い原材料ではありません。
「使用されているから、粗悪なペットフード」でもありません。
たとえ仮に「羽、内臓、頭、足」などが含まれていたとしても、
もともと自然(野生)下では、猫や犬はそれらを食べていたのですから、猫たちからすれば、
それらは本来の食事といえるのではないでしょうか・・・。
結局どのフードにも「合う」「合わない」がある、というだけです。
理解し、納得して選ぶこと
安いフードを食べさせていても、長く生きてくれる子もいれば
高いフードを食べさせてあげていても、病気になってしまう子がいます。
どんなに良いと言われているフードであっても
その猫によっては、危ないフードになるうるものだってあります。
問題は
そのフードが、その猫の好みに合っているのか?
その猫の体調に合ったフードを食べられているのか、どうか?
なのではないでしょうか?
大切なのは、理解し、納得して選ぶこと。
また「これなら、自分も食べられるかな?」という視点をもって選ぶこと。
私(飼い主)たちの役目は、あふれる情報に惑わされることなく
我が子の好みや体調に合ったフードを探してあげることだと思います。

こちらは
服部幸先生が【著者/編集】として出されている書籍です

「げぼく」の教科書では、フードのことをはじめ
健康で長生きさせる心得、環境づくりの心得
そのほか気になる興味深い雑学などなど
獣医さんが書いた本なので
ネットで調べるより信頼できる、まさに「教科書」です