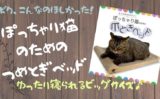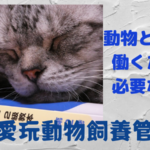猫と一緒に暮らすからには、家の柱や壁、家具などがいたむ覚悟をしなければなりません。
なぜなら

ボクらの「爪とぎ」という習性は、誰にもやめさせることはできニャイのだっ!
猫がなぜ壁や柱、家具で爪とぎをするのかって・・・それは、ね。

ボクら(猫様)なりの「大事な理由」があるからにゃのだ

猫が爪とぎをする理由
出し入れ自由な猫の爪のしくみ

そのまえに。
器用に出し入れできる猫の爪のお話をしますね。
普段は靭帯にひっぱられて引っ込められている猫様の爪。

「狩り」や「爪とぎ」の時には、爪を支える骨の下にある腱(けん)を後ろ側にひっぱることで・・・

「ぅにょーん」と出てくる仕組みになってるんだ、すごいでしょー


ボクたち「猫」は、足音をたてずそーっと静かに歩くために、普段は爪をしまっておくんだよ。
だって、獲物を捕まえる時に足音がしたら、逃げられちゃうからね

途中まで静かに近寄っても、とびかかる直前の走行がどすすんっ☆と騒々しいから、結局は逃げられちゃうけどね。

・・・・・。
猫様たちは、
爪をしまうことで足音を立てずにそーっと歩き、獲物に近づいて
狙いをさだめ、ぶわっ!ってとびかかる時に、ご自慢の爪をしゃきーん!って出すのです。
しかも!
猫様の爪は、獲物を押さえ込むために鋭くとがっていて湾曲しているんだよ。

あとボクがぅにょーんって爪を出すのは、夜中、寝ているおかーちゃんの顔を突っつく時!

・・・地味にいたいのよ、それ。
猫が爪とぎする理由
そんな猫の爪は、何層もの角質が重なってできています。
内側で新しい爪が伸びてくると、外側のすり減った古い爪を剥がそうとするために「爪とぎ」をします。

それでもなかなか剥がれない時は、噛んでひっぱっちゃうんだ

また、狩猟時代の猫にとって爪は大事な武器でした。
なので、いつでも鋭くとがらせておく必要があり、そのために「といでいる」といった意味もあるのでしょう。
ほかにも爪とぎをする理由には、ただ退屈しているときの気晴らしだったり、寝起きの準備運動だったり、ストレスが溜まったり興奮したりした時の「転移行動」としての場合もありますが・・・
猫にとって「爪とぎ」をする最大の理由は

ボクたちがお庭の木や、お家の壁や柱、ところかまわず爪とぎをするのは、テリトリーを確認するための匂いをつけるためのマーキングのためなんだ。
猫の肉球には強いニオイを放つ臭腺があり、爪とぎをすることで臭腺のニオイをつけ自分の縄張りを主張しているのです。
また残った爪跡にも、縄張りを主張する意味があります。
つまり、肉球から出る「分泌物」による嗅覚的マーキングと、爪とぎ跡の視覚的マーキングです。
なので、猫が柱や壁、ソファーなどの家具に「マーキングしたいのにゃ!」と思って爪とぎをしていたとしたら、爪とぎ器があろうがなかろうが関係ないのです。
壁や柱など垂直なものに爪とぎをするときには、できるだけ背伸びをして高い位置にマーキングして「ボクは大きいんだぞ。ケンカも強いんだからなっ!ふふーん♪」とアピールするのです。
なので、どんなに怒ったところで「爪とぎ」という習性をやめさせることはできないのです。

爪とぎ被害対策
爪とぎには「マーキング」という意味もあるため、家の中で爪とぎをする場所はだいたい決まってきます。
ですので、その場所に「爪とぎ専用アイテム」を置き、猫がそれ使うようになれば、爪とぎによるボロボロ被害を減らすことができます。(でも残念ながら、完全には防げません。)
爪とぎをやめさせるのではなく、「ここでなら、爪とぎしてもいいよ」という環境を作ってあげましょう。
市販の「爪とぎアイテム」には、猫が大好きな段ボール製のもの、爪のひっかかりやすい麻の縄を巻いたポールタイプのもの、ループのあるカーペット地を張ったものなど、さまざまな種類があります。
段ボール製で壁につける(縦置き)タイプのもの。
こちらも段ボール製で、ベッドとしても使える横置きタイプのもの。
半分から上が縄で下がカーペットを巻いたタイプ。
どうやら多くの猫は、「段ボール製」のベッドにもなる横置きタイプがお好みのようです。
どれが好みかはその猫によっても異なりますので、いろいろ試してお気に入りの一品を見つけてあげたいですね。

ボクは、自然の木のほうが好き!
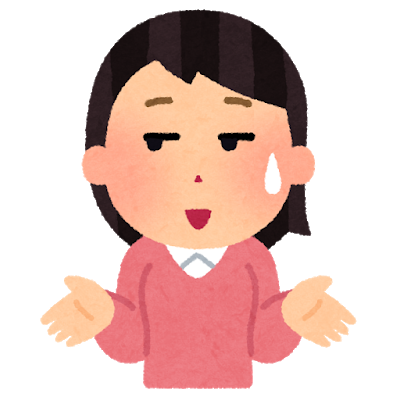
うちの子たちは、ふすまドアの縁で爪とぎするのが好きなので、「木の板」を打ち付け、定期的に交換してます(苦笑)
壁の保護シートというものもあります。
爪とぎをしてほしくない壁に貼って使用するのですが、猫は高い所に体を伸ばして爪とぎするのが大好きなので、猫の体長(手が届く)ぐらいの高さまで貼るようにしてくださいね。
猫の爪とぎ。やめさせることはできないよ
猫にとって「爪とぎ」は本能からくる習性なので、やめさせることはできません。
柱や壁で爪をといで傷とつけたからと、大きな声で怒ったり、叩いたりしないでくださいね。
大事なのは爪とぎをやめさせるのではなく、「ここでなら、いくらでも爪とぎをしてもいいよ」という場所をつくり、誘導してあげることです。
爪とぎ器や保護シートなどの対策グッズを上手に活用することで、猫もヒトもリラックスし、笑顔で暮らせる環境つくりをしましょう。
でも、爪とぎの場所を用意してあげても、手近な場所で爪とぎをしてしまうこともあります。
ヒトの思うようにはいかない。それが「猫」なのです。