人と動物との関係学

Human Animal Bond
ヒューマン・アニマル・ボンド
あまり聞きなれないかもしれないけれど
この言葉は近年、メディアでも取り上げられるようになり
『人と動物の絆』という意味。
コンパニオンアニマルの社会的認知を高めるとともに、
人の暮らしの中に動物と触れあうことで得られる効用を活用しようという、
活動の根本となる考え方なんだ。
単にボクたち動物を「受渡しや保護の対象」としてだけではなく
ボクたち動物と、
人間との「かかわりあい」そのものに焦点をあてようとする人たちが増えてきたんだ。
【関係学】とは何か
「人と動物の関係学」という分野は、1960年代の終わりから1970年代の初め頃
ボクたち動物と人間とのかかわり合いを整理、分析するために、
動物が、
人間の精神や肉体に大きな影響を与えるものであり、
ヒトと動物は常に互いに影響し合っている。
この「関係学」を研究、調査の対象とする科学者たちが増え始めてきたんだ。

そんな科学者たちのひとり
アメリカの臨床心理学者:ボリス・レビンソンはこの分野で活躍した開拓者の一人。
ボリス・レビンソンをはじめとして
〇 教育
〇 動物愛護
〇 獣医学
〇 医療
〇 人間の福祉
〇 行政
〇 環境・・・
さまざまな分野にいるいろいろな専門家たちが医療や教育など、
あらゆる背景における「ヒトと動物の相互作用」を、しっかりと見ていくことの大切さを認識。
1974(昭和49)年以来、
幅広く専門家を集めた国際会議を開いてきたんだ。
この時期に、
ヒトと動物の関係そのものを客観的に検討するための組織
アメリカの ペットパートナーズ
イギリスの コンパニオン・アニマル研究会
などに代表される
人間と動物、環境の相互作用に関する「教育研究活動」を目的とした
人と動物の関係そのものをより客観的に検討するための組織が誕生したんだ。

人と動物との接点
人と動物の関係は、
もっと正確に言えば
「人と動物の関わり合いにおける互いの接点」
と、言うべきものかもしれません。
ボクたち動物と、人間とはさまざまな「接点」を持って生きていてる。
おかぁちゃんたちのように
ボクたちを「ペット」として育ててくれるのも、「接点」のひとつ。
また、生きていくために
牛さんやブタさん、鶏さんの「お肉」を食べるのも、「接点」のひとつ。
その他にも
お薬の開発のための実験動物
学校で飼育する動物
野生で生きる動物たち・・・
それは直接的・間接的に関係なく、
人間はボクたち動物たちとなんらかの「かかわり」を持たざるをえない。
だって地球の上には、人間だけでなく

ボクたち「動物」だって、ちゃんと生きているのだから。

それぞれの「接点」のつながり
それぞれの分野には、それぞれの専門家がいて
愛玩動物って呼ばれる「ペット」の医療を専門にする獣医さんは
ボクたちが病気になったとき、ボクたちをただ治すだけじゃなく
おかぁちゃんのように、
横でオロオロするだけの飼い主さんを励まし、支援してくれたり、
時には「そんな育て方はダメ!」って叱ってくれたりもする。

まぁ、
おかぁちゃんの耳には、あまり届いてないみたいだけど
産業動物や実験動物って呼ばれる子たちにだって、
ちゃんと専門の獣医師さんがいたりするんだ。
それぞれの「接点」がいかにつながっているか。
また、それらに共通する理念や思想はなんなのか?
それをちゃんと理解するのと同時に、
それぞれの専門分野に対しての「接点」の存在を無視して、ボクたちとの関係の発展はありえない。
ということを伝えていくのが、
ヒトと動物の関係学が果たすべき役割なんだって。
参考文献:愛玩動物飼養管理士テキスト2級-1

ボクたちの「もしも」の時のために
保険に入ることも検討してみてね

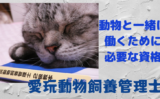
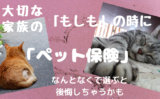

-150x150.jpg)